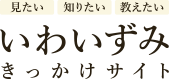TOP > 岩泉町地域おこし協力隊 > 畜産インターン@岩泉2025(岩泉町地域おこし協力隊インターン)報告レポート2
畜産インターン@岩泉2025(岩泉町地域おこし協力隊インターン)報告レポート2
9月に実施した畜産インターン@岩泉2025のレポート2人目です。
一人目のレポートはこちら
今回参加してくれた学生は、岩手大学動物科学科の学生なので、みなさん大学4年間で、動物や畜産について学ぶわけですが、実は大学でも実際の家畜に触れることはそんなに多くありません。特に今回岩泉で触れた、短角牛や黒豚については、ほとんど触れる機会が無いと言っても過言ではないでしょう。そんなこともあり、学生たちは直接家畜に触れられる機会をかなり楽しみにしていました。学生たちが岩泉町をフィールドに興味のある事を学び、それが将来の役に立つのであれば、とても嬉しいことです。

岩手大学 農学部 動物科学科2年
畠山彩音
1. 参加のきっかけ
私は現在、持続可能な畜産の実現に向けてアニマルウェルフェアの観点からの飼養管理に興味を持ち、大学の講義を通じて理解を深めてきました。その中で、書籍やインターネットから得られる知識が必ずしも現場の実態と一致しているとは限らないのではないか、また、実際に現場を経験することで初めて見えてくる課題や気づきがあるのではないかと考えるようになりました。そこで、畜産現場の実情を自らの目で確かめ、現場で働く方々の声を直接伺うことを目的として、本インターンシップに参加しました。
また、将来的には畜産分野での就職を目指しているため、今後の進路選択に活かすためにも貴重な機会になると思い、参加することにしました。
2. 作業内容
① 龍泉洞黒豚ファーム
豚舎の清掃
給餌
豚の移動
豚熱ワクチン・抗生物質・鉄剤注射の補助
去勢の補助
② 工藤牧場
牛舎の清掃
給餌
牛舎の床材(敷き藁・もみ殻)の交換
獣医師の作業見学(エコー検査・直腸検査など)
窓の清掃・石灰消毒
搾乳体験
③ 阿部牧場
牛舎の清掃
給餌
子牛への授乳
床材(おがくず)の運搬
出荷前の牛の洗浄見学
④ その他
・ガイダンス
岩泉町の畜産および農作業中の安全について
・短角牛・黒毛和牛生産農家(佐藤あきえさん宅)での研修
放牧地・牧草地の見学
牛舎の見学
・兜森放牧地(大川肉牛生産組合)
駆虫剤(バイチコール、アイボメックトピカル)塗布
ワクチン(牛5種混合生ワクチン)注射の見学
・短角和牛・黒毛和牛生産農家(佐藤文喜さん宅)での研修
削蹄の見学
子牛への授乳
牛舎の清掃
床材(敷き藁)の作成

3. 感想
今回のインターンシップを通じて、農家の方々が日々どのような工夫や苦労を重ねながら畜産を営んでいるのかを実際に体験できたことは、私にとって最も大きな収穫でした。畜産といえば、広大な土地で牛がのびのびと育てられているというイメージを持っていましたが、岩泉では山間部という地形や冬の厳しい気候など、地域特有の自然環境を巧みに活用しながら畜産を営まれていることを知りました。
私はこれまで、持続可能な畜産の形態の一つとして放牧やフリーストールを理想的だと考えていました。しかし実際に現場を訪れ、農家の方々の話を聞くことで、作業量の多さや移動時間の長さといった、理想の裏にある現実を自分の目で確かめ、そのメリット・デメリットを体感することができました。山での放牧は、環境や動物にとって良い面がある一方で、ウシの健康管理や水飲み場・牧柵などの設備整備といった課題も伴います。たとえば、「まぶりさん」と呼ばれる方が毎日見回りを行い、異常があれば農家の方に連絡し、農家の方も月に一度は牛の健康管理や移動のために山に登るそうです。山への道は途中まで舗装されていますが、大部分は車で1時間以上かかる山道であり、日々の管理には大きな労力が必要です。私はこれまで放牧の良い面ばかりに目を向け、日々の管理の大変さについては考えが及んでいなかったことに気づかされました。今回の経験は理想と現実のギャップを認識しなおす貴重な機会となりました。
また、農家の方をはじめ、獣医師や削蹄師、県の農業改良普及員など、畜産に携わる多くの方とお話をする中で、アニマルウェルフェアに配慮した持続可能な畜産の実現は、農家だけに負担を強いるのではなく、消費者や行政を含めた社会全体で取り組むべき課題であると改めて感じました。消費者には、畜産物がどのように生産され、なぜその価格なのか、また数ある畜産物の中からどのように選ぶべきかを考える責任があり、行政は一方的に政策を押し付けるのではなく、現場の声を丁寧にくみ取ったうえで制度設計を行う必要があります。そして農家は、環境や消費者の声に柔軟に対応していくことが求められていると思います。日本の畜産業は、労働力不足や飼料価格の高騰に加え、環境負荷の低減や動物福祉への配慮など、多くの課題に直面しています。さらに、安価な輸入肉の影響で国産畜産物は選ばれにくくなっている現状もあります。「昔からこうしているから」「うちは大規模農家ではないから」と現状維持にとどまっていては、課題の解決や付加価値の創出にはつながりません。むしろ、異常気象などの地球温暖化に対応し、持続可能性やアニマルウェルフェアに配慮した安心・安全な畜産物を求める消費者の声に耳を傾け、管理方法の見直しや新たな技術の導入に積極的に取り組むことが生産性の向上や差別化による付加価値の創出につながると思います。さらに、今回のインターンシップで私たちが学んだように、生産プロセスの「見える化」を進めることで、消費者からの信頼や理解が得ることができるだけではなく、価格の受容にもつながると思います。
今回の経験を踏まえ、私自身も一人の消費者として、また畜産の現場を体験した者として、持続可能な畜産の在り方について改めて考え続け、何が最良の選択かを問い続けていきたいと思います。
インターンシップに参加する前から畜産分野での就職を視野に入れていましたが、今回の活動を通じて、畜産農家だけでなく獣医師や削蹄師、公務員など、さまざまな立場から畜産に関わる方々のお話を伺うことができました。それにより、自分が将来どのような立場で畜産に関わっていきたいのかをより深く考えるようになりました。今後も積極的に見聞を広め、さまざまな考えや活動に触れながら、自分の目標を達成できるようなキャリア設計をしていきたいと思います。
4. 謝辞
今回のインターンシップにおいて、温かく受け入れてくださった龍泉洞黒豚ファームの皆様、工藤牧場の皆様、阿部牧場の皆様、短角牛・黒毛和牛の生産農家の皆様、お忙しい中にもかかわらずご対応いただき、誠にありがとうございました。作業内容のご指導や、私たちの質問に対する丁寧な説明を通じて、畜産現場に携わる皆様のリアルな声を直接伺うことができ、また実際の作業を体験する中で多くの学びを得ることができました。
また、岩泉町ならびに KEEN ALLIANCE の皆様にも、このような貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。岩泉町や畜産との関わりについて詳しく教えていただいたり、皆様との会話の中から新たな気づきを得ることができたりと、大変有意義な時間を過ごすことができました。送迎やミーティングなど、インターンシップ中のさまざまな場面でも大変お世話になりました。
参加前は期待とともに不安もありましたが、今は「間違いなく参加して良かった」と自信をもって言えます。改めて、このインターンシップに関わってくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

 いわいずみ
いわいずみ